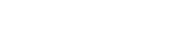「ブッダよ、来てください」
道元禅師の『正法眼蔵 生死』の「ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて~」(p. 1〈注1〉参照)と同じ意味の詩を、ティク・ナット・ハンさんも詠っています。
ブッダはあなたのなかにいます。
ブッダは呼吸の仕方も優雅に歩む方法もご存知です。
あなたが忘れていても、ブッダよ来てくださいとお願いすれば
すぐに駆けつけてくださいます。
待つ必要はありません。
――ティク・ナット・ハン師「瞑想の偈」
ブッダに呼吸してもらい
ブッダに歩んでもらう
わたしが呼吸することはない
わたしが歩むこともない
ブッダが呼吸している
ブッダが歩んでいる
わたしは呼吸を楽しむだけ
わたしは歩みを楽しむだけ
ブッダは呼吸
ブッダは歩み
わたしは呼吸
わたしは歩み
ここにあるのは呼吸だけ
ここにあるのは歩みだけ
呼吸している人はいない
歩いている人はいない
呼吸しながら安らいでいる
歩きながら安らいでいる
安らぎは呼吸
安らぎはあゆみ……(島田啓介・訳)
この詩は、僕にとっても大切な応援歌となっています。
僕たちが瞑想を楽しめるためには、ブッダにやってもらわないといけないのです。僕らがすべてを自分でやっていたら、余裕が持てずに、楽しむ暇を失ってしまうからです。

藤田一照師の指導で坐禅を実践する参加者
道元禅師の「安楽の法門」とは
――呼吸しながら安らいでいる。歩きながら安らいでいる。(ティク・ナット・ハン)
道元禅師の「坐禅は安楽の法門なり」の〈安楽〉が、ここに見事に活写されています。
この詩によって、「安楽の法門」にどういうふうにして入るのか、どこに安楽の法門がみつかるのか? ということのヒントが与えられています。
坐禅の時の「調身・調息・調心」。あとは身と同じ態度で、息にも心にもアプローチしていくということになります。「調息」に関しては、正しい姿勢をしていれば、体が勝手に呼吸してくれます。「調身」は、呼吸の邪魔にならない姿勢の実現ともいえるでしょう。
息を吐いていったら、吐く息が自然に終わるまでじーっと見守っている。自分で一生懸命わざと長く吐くのとは違います。自然に息が出ていくのと自分で意識的に吐く、この区別は非常に微妙ですがとても大事です。自分が、意図的に長く吐こうとしているのか、息が自然に長くなっていくのか。ここの微妙な違いに注意を払うべきです。吸うときも、勝手(自然)に入ってくるのと、自分が作為的にそうしているのとの違い。この微妙な違いが非常に大切になってきます。
調息の鍵は、吸う息と吐く息のあいだにあるスペースです。日本文化の伝統で〈間〉と呼ばれるものです。これをどのくらい大切にできるかというところにかかってきます。自然に生まれてくる〈間〉。このスペース〈間〉は、吐く息と吸う息のあいだに自然に生まれてくるものです。吐く息と吸う息とのあいだに、我慢あるいは意識して、無理に息を止めるというようなものでは決してありません。
姿勢も呼吸も自分が調えるというよりは、ブッダ(内なる自然)が調えてくれる。しかし「内なる自然」と言うと、内と外を区切るようなニュアンスが生まれてしまいがちです。身体の「内なる」自然は、外側の自然とひと続きなので、たんに〈自然〉とだけ言ったほうがいいかも知れません。自然は、内と外に区切れるようなものではないからです。
そして「調心」。もう、ここまで来ると、すでに調えられた「心」そのものです。自然に姿勢と呼吸に心が優しく寄り添っているからです。
坐禅のときは、意図的なコントロールを最大限に減らしていく。ゼロではないが最小限にするわけです。でも、もちろん寝てしまっては、元も子もありません。
エゴ(吾我)は自分のお得意とする意図的なコントロールが手放されてしまうと、普通、ふてくされて寝てしまうか、考え事をして時間を潰そうとするかです。ですから、何もしないことは非常に難しいのです――絶対何かをします、この〝エゴ〟は。その理由は、意図的なコントロールが最小限になった状態は、〈エゴ〉にとっては、極めて居心地が悪いからに他なりません。その当のコントロール感こそがエゴの温床だからです。だから、最大限の注意を払って、エゴの尻馬に乗らないようにしましょう。

会場からの質疑応答で、プラムヴィレッジの僧侶と意見を交換する藤田一照師
「非思量」~Beyond thinking
意図的なコントロールを最小限にした状態。これは、道元さんの言い方だと「非思量」になります。「考えの向こうに行く」。考えを消すのではなく、考えの向こうに行く、ということです。
「長空不礙白雲飛」
――長空、白雲の飛ぶを礙えず(*2)
長空は白雲が飛ぶのを邪魔しない。大空は、自分のもとで白雲がどのように飛ぼうとも、それにとらわれることもなく、また邪魔もしないという、大らかな心をもっているという意味です。
*2「長空不礙白雲飛」
一照師が、Web上に建立した禅寺「大空山磨塼寺」の山号のヒントとなった禅語。「大らかな心をもって、塼(中国で粘土を焼き作った灰黒色の煉瓦〈れんが〉。日本では、斑鳩の寺院跡や鎌倉唐様建築にみられる)に譬えられる〈いのち〉を磨く場という意味と師の願いが、この「大空山」という山号には込められている。
「思いは頭の分泌物」(*3)ですから、そのまま浮かぶまま、消えるままにしておくということです。しかしそれは、頭でやることはできない。姿勢と呼吸の助けを借りてやるということになります。坐禅に何かを求めて坐っていると、必ずそこで、求める思いが湧き出てくる訳ですから、何かを求めて坐っている限り、「マインド・ゲーム」の中でやっていることになる。それでは、 beyond thinkingにならないのです。
*3 「思いは頭の分泌物」
内山興正老師(安泰寺第六世堂頭1912~98年)が、晩年に辿り着いた境地から坐禅の要諦を語った言葉の一つ。安泰寺で出家得度した藤田一照師は、内山老師の孫弟子に当たりその法灯を継ぐ。以下、内山老師『正法眼蔵 山水経・古鏡を味わう』 p. 98より。
「悟りにしても、いったん悟ったらもう迷うことはない、悩むこともないなどという、そんなつっぱった悟りでは困る。生きている悟りというのは迷えば迷える。悩むとき悩めるという悟りでなければならない。それではじめて生き生きした悟りです。生き生きと生で生きているということは、人間理性をもっているのだから、その理性をもって分別しながら、一切を無相として見ている、つまり分別を解脱しているということです。言い換えれば、いろんな人間的思いを頭の分泌物として眺めるということだ。
(下線、編集部)
道元禅師の言う「非思量」“Beyond thinking”になるためには、身体の自然と呼吸の自然に重心を置く、これしか方法はありません。意識にとっては「完全な明け渡し(total surrender)となります。道元禅師の言う「ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて」、ティク・ナット・ハン師が詠った「呼吸しながら安らいでいる / 歩きながら安らいでいる」。こういうことが、じつは禅にとって一番の大事なことなのです。僕はティク・ナット・ハン師とのご縁に触れて、それを教えていただきました。
Issho, smile! Practice should be enjoyable.
僕は今も、ティク・ナット・ハン師に掛けて頂いたこの言葉に導かれて、禅の道を参究しています。
(調講演2 了)