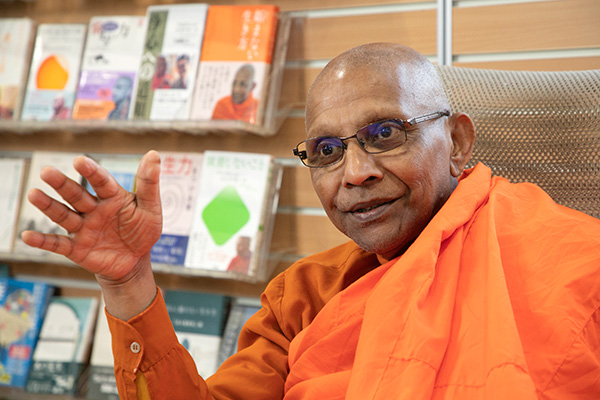「私はいない」。そこらへんが、僕が最初にティク・ナット・ハンに出会った時に、衝撃的に惹かれた理由です。
というのは私の前史というか、私がティク・ナット・ハンに出遭ったのは30代の初め頃、1990年ころですけれど、その前に自分の前史があって。それまで僕は〝自分〟ということに苦しんできたのです。

どういうことかというと、19歳の頃、双極性障害(かつては躁うつ病とも呼ばれていた)を発症して、ずっと精神的な病気で苦しんできたのです。1979年から80年頃にかけて2年間、20歳から21歳くらいまで入院していました。
当時は、精神医療がオープンではなく、今とはずいぶん違いました。今は自分が発達障害であることなども、比較的オープンに言える状況になってきましたから。
当時は、精神病にかかった者は社会から排除されるような時代です。精神医療も今から比べるとずっとプリミティブで、治療を続けていって治るかどうかも分からない。そういう状態で、20歳前後の青春のまん中を閉じ込められた環境で、強い薬を飲んでぼーっとしながら過ごすという絶望感――そこから、僕はスタートしているのです。
退院後に大学は退学しましたから、それから先何をするという展望もありません。籍を置いていれば大学に戻ってなんとか卒業しようかという発想にもなりますけれども、それもない。かといって、就職とか考える状態でもない、もちろん苦しむわけです。
同級生は今頃、何をしているだろうということが思われる。病気だし、どうしようとぐるぐる考えても、頭のなかは不安でいっぱい。現実は少しも改善していきません。当時は、福祉というのがありませんでした。精神疾患の一部が障害者基本法によって障害と認められたのが1993年です。その前は社会復帰のための回復を担うはずの福祉サービスがないのです、基本的に。
自発的にやっていた人はいますけれども、制度としてはありませんでした。ソーシャルワーカーが来て「退院ですね。どうしましょうか、まず作業所に行ってみましょうか」とアドバイスしてくれたり、職業訓練を受けて「障害者枠で就職をしましょうか」みたいな支援は全くないのです。障害者ではないのですから、単なる病人なんです。非常に社会的には適応しにくい病気でしょう? それなのに退院後のサポートもない状態で世界に放り出されて、まったく自己責任100%になっていたわけです。家族もどうしたらいいかわからない。
バックナンバー「 インタビュー」