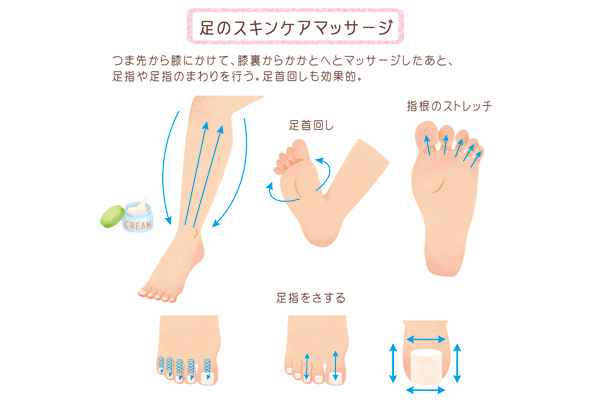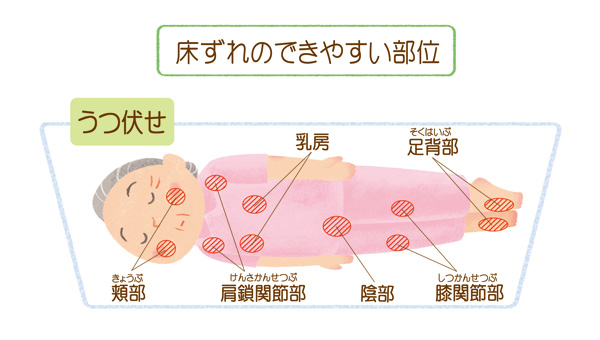道義の力
わが家はじつにさまざまな人が出入りしていました。政界の黒幕から旧日本軍の高級参謀や旧満州(中国東北部)帰りの革新官僚、労働組合のボスなど、戦後史を彩った人びとが訪ねてきたものです。しかし、父は黙々といつもと変わらぬ態度で、客人と相対していました。
坑内から採炭作業を終えたばかりの坑内作業員の方々がわが家を訪ねてきたことがありました。彼らはヘルメットを手にしたままで、顔も真っ黒でした。父は快く彼らを座敷に招き入れ、床の間を背にした上座に案内し、一升瓶を持ってお酌をして回っていたのです。どんな大物でもそんな振る舞いをしたことのない父ですが、彼らこそ、かけがえのない大切な人たちだったのでしょう。
戦後間もなくは「黒いダイヤ」といわれて、石炭需要は膨らむ一方でしたが、やがて高度成長を迎えた日本では、炭鉱も次第に傾いていき、閉山に追い込まれていきました。炭鉱主と炭鉱従業員の語られぬ間柄は、記憶にとどめておいてもいいかもしれません。教科書には、「総資本対総労働の対決」と書かれていますが、現実はもっと人間臭いものでした。
こんなこともありました。父が亡くなったあとのことですが、角帽に学生服の大学生が訪ねてきました。その学生さんは自分の学費を出してくれていた父の遺影にお線香をあげに来てくれたのです。僕たち家族は何も知らなかったのですが、学生さんは炭鉱労働者のご子息で、大学を卒業するまで学費を出す約束を父が果たしてくれたとのことでした。
僕がワシントン支局長のときも、取材先ではカメラ・クルーの機材も1人で担いでいましたが、欧米の取材チームからは好奇の目で見られたものです。それでも、これこそわがスタイル。父から学んだ「道義の力」です。人としての姿勢は、外交の世界にも通じると信じています。