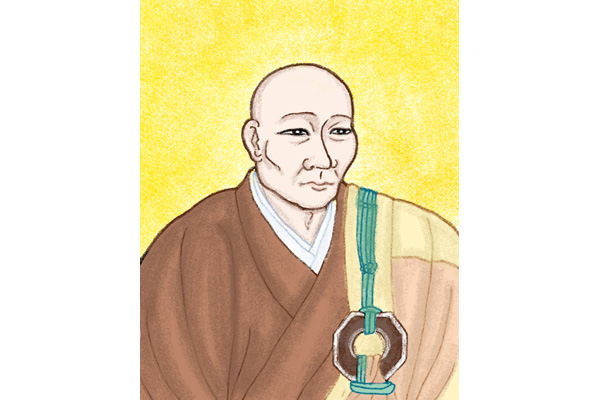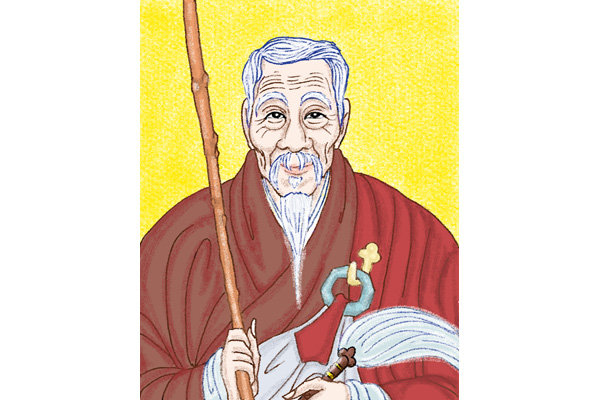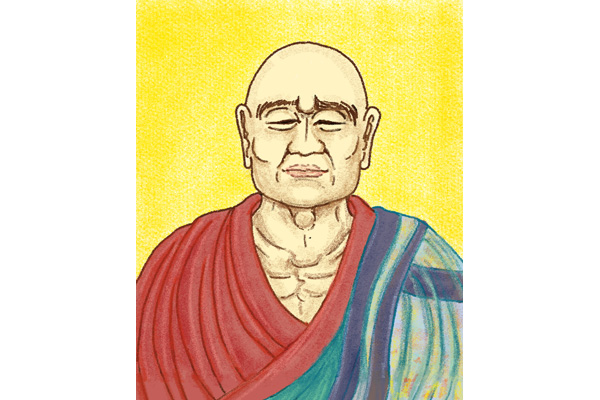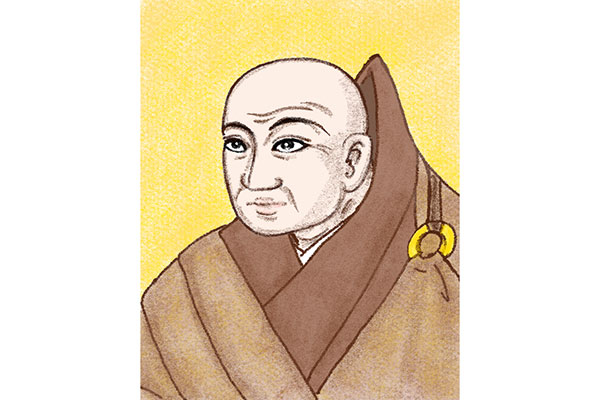修行僧としての悩みと決意

慈円が入寺し、後に住職を務めた青蓮院門跡(写真提供・PIXTA)
千日入堂の大願をはたした慈円は、法性寺の座主に任じられます。法性寺は藤原家が建てた寺院で、兄の九条兼実が寺内に邸宅を構えていた所で、のちには孫の九条道家が東福寺を創建しています。
ところが慈円は、なぜか隠遁の心にかられたのです。
「いっさいの僧位を辞退して、深い山里で静かな余生を送りたい」
25歳の慈円が思いあまった表情で切り出したとき、兼実は驚きました。
「叡山でなにか面白くないことでもあったのか」
「いえ、ただ私は仏法を興隆する器ではないことを自覚したのです。私の生涯は無益なので、それで…」
「愚かなことを考えるでない。器はそなたが望めば、いくらでもあるではないか。いまは異母兄の近衛や松殿が繁栄しているが、私も摂政関白の機会をうかがっておる。そうなれば、そなたは天台座主の器になれるのだ」
こんな問答が2年ほどくり返され、ついに慈円は兄の意見をいれて、隠遁を断念したのです。これは天台僧として、兄の兼実の朝廷での出世と形影(けいえい)を共にすることを意味したのです。
平清盛が亡くなった養和(ようわ)元年(1181)、各地が未曾有の飢饉に見舞われたころから、平家が壇ノ浦で滅亡した文治(ぶんじ)元年(1185)までの4年間に、慈円は極楽寺、法興院の別当、三昧院、成就院、無動寺の検校(けんぎょう)に任じられ、青蓮院(しょうれんいん)、白川坊、善峰(よしみね)寺の住職を兼務しています。
そのころに詠んだ歌が「百人一首」に入っています。
「おほけなく うき世の民に おほふ哉 わが立つ杣に すみ染の袖」
身のほどもわきまえず、墨染めの衣で万民の安穏を祈り、仏の慈悲をおおいかけよう、というものです。「わが立つ杣」は、延暦寺を開いた最澄の仏法を継いだものとしての自信と情熱がこめられています。この自信から、こんな歌も詠んでいます。
「世の中に 山てふ山は 多かれど 山とは比叡の み山をぞいふ」
慈円には、もはや隠遁などという思いはありません。比叡山の器に入って、それに実を入れるぞ、という自覚にあふれています。ちなみに慈円が詠んだ歌は6000首をこえ、『拾玉集』という家集が編まれています。
バックナンバー「 日本仏教を形づくった僧侶たち」