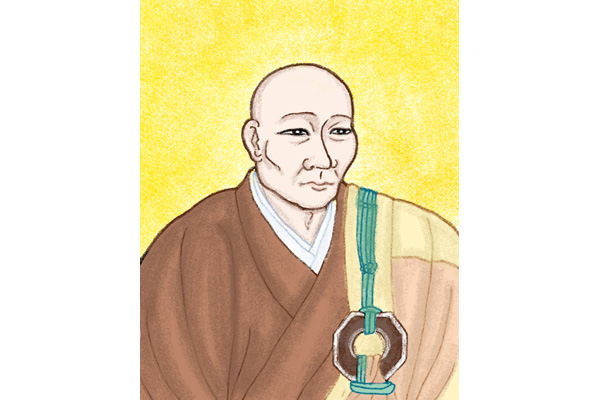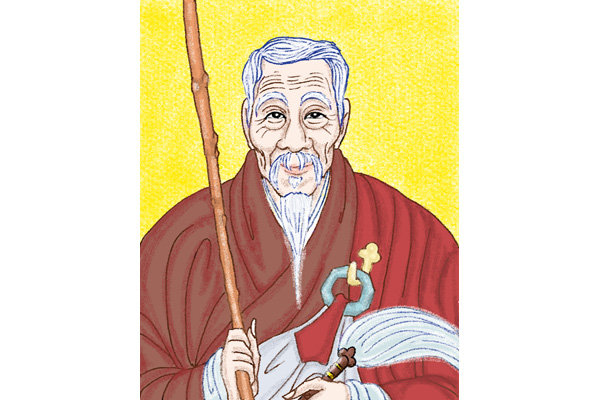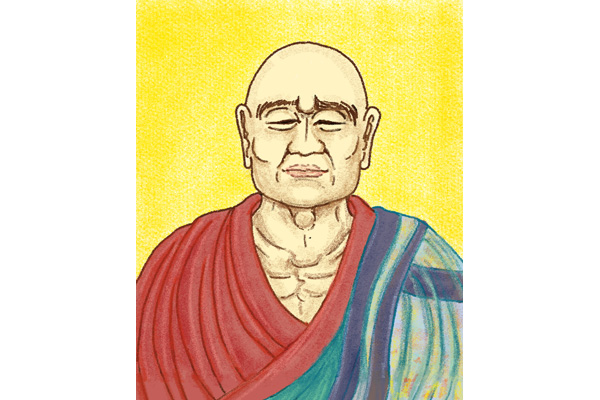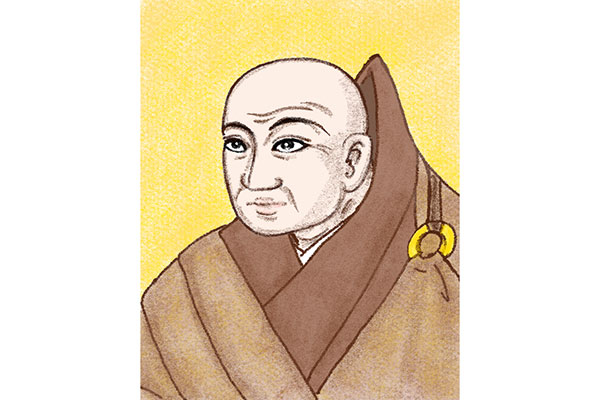鎌倉幕府と朝廷の和を図る

比叡山延暦寺の根本中堂(写真提供・比叡山延暦寺)
鎌倉三代将軍の源実朝(さねとも)が甥の公暁(くぎょう)に殺されたのは、承久(じょうきゅう)元年(1219)正月のことです。鎌倉将軍の死は、後鳥羽上皇にとっては、天皇政治を回復する絶好のチャンスと見て、幕府と対決する意志を固めました。
一方、幕府は実朝の母の北条政子(まさこ)が執務を代行し、北条義時(よしとき)が補佐する体制をとります。いわゆる尼将軍と執権政治です。しかし、将軍が不在のままで政治を行なうのは得策でないと考えた政子らは、後鳥羽上皇の皇子を将軍に迎えたいと希望しますが、幕府の潰滅を意図する上皇は、その申し出を拒否したのです。
そこで白羽の矢が立てられたのが、九条兼実の孫の道家の子で、わずか2歳の頼経(よりつね)です。これが、いわゆる藤原征夷大将軍の第一代目となるのです。この擁立に慈円が絡んでいたかどうかは分かっていません。
しかし、慈円は長年にわたって後鳥羽上皇と親交を持ち、摂政格としてなにかと相談にあずかっていました。さらに歌人として著名な藤原定家(さだいえ)らと共に、いわゆる「新古今和歌集」の時代を開き、上皇の厚い信頼をかちえていたのです。
源平の争乱から、鎌倉幕府の成立まで、激動の世と共に生きてきた慈円は、時代が武力をもつ武家政治の方向に流れていることを鋭く見抜いていました。
「鎌倉幕府と協調しなければ、朝廷政治は成り立たない。もし討幕などを考えて、戦を仕かければ、源平争乱の比ではなく天下は混乱するだろう。幕府の力をあなどってはいけない」
現実主義者の慈円は、幕府と朝廷が調和する「公武合体論」が持論です。慈円は、ことあるごとに血気にはやる上皇をいさめます。ところが、上皇の討幕の意志は固く、しだいに慈円をわずらわしく思うようになり、身辺から遠ざけたのでした。
そこで慈円は、上皇の考えをあらためさせるために、『愚管抄』を著わしたのです。
この書は、神武天皇から当時の順徳天皇までの歴史の推移を「道理」という考えからとらえた歴史書です。
「一切の法(真理・存在・規範の意味)は、ただ道理という二文字がもっている。その外にはなにもない」
慈円は、歴史のすべての事実や事件は、道理が現われたものとして、正当視します。いわば、「あるものをある」と認める現実主義の考えがあったのです。
たとえば、仏法によって政治を行なうと考えた蘇我氏が、それに反対する物部氏を倒したのも、仏法を中心とする道理の現われであり、そのことで聖徳太子の執政を生み出し、仏法と王法(政治)が守られたと考えます。
また、歴史が天皇親政から、しだいに摂政関白による摂関政治に移行したのも、幼い帝を支えるための道理である。さらに、保元・平治の乱で武士が台頭し、鳥羽法皇以後は武士が天下を制するようになったのも「武者の世の道理」になったからだ、と慈円は説いています。
「いまは武者の時代です。この現実を無視しては、天皇家の将来に重大な影響を及ぼすかもしれません」
慈円は、このような意味を含めて『愚管抄』を著わし、後鳥羽上皇に討幕を思い留まらせようとしたのです。『愚管抄』は、承久2年(1220)ころに成ったといわれています。
ところが、慈円の諫言もむなしく、翌年の5月、承久の乱が起こり、後鳥羽上皇軍は、幕府軍によって惨敗し、後鳥羽上皇らは流罪になったのでした。
慈円は自分の一生をかえりみて、
「名利の二道をあゆむ」
と素直に告白しています。慈円は嘉禄(かろく)元年(1225)、71歳で名誉と利得の「名利」に満ちた生涯を終えたのでした。
バックナンバー「 日本仏教を形づくった僧侶たち」