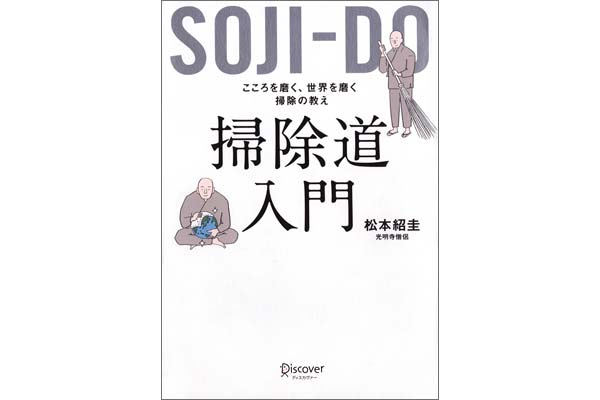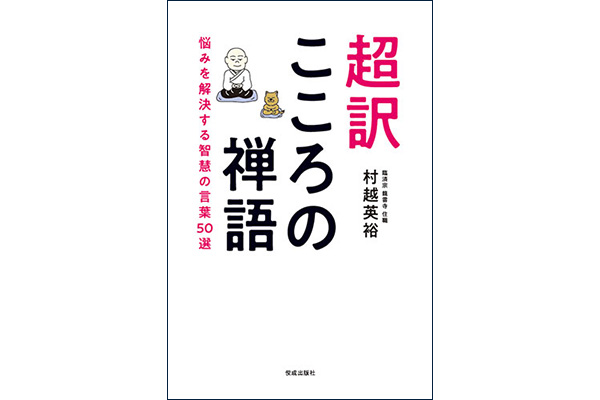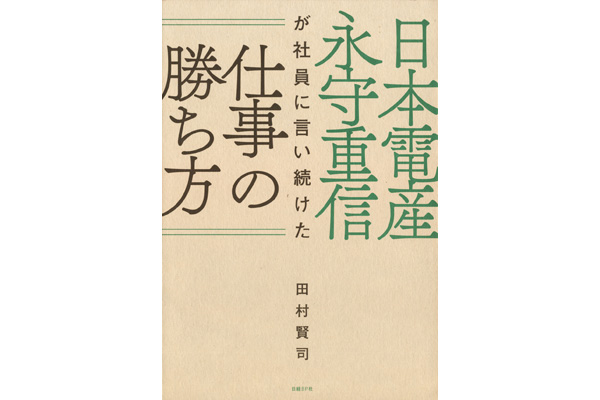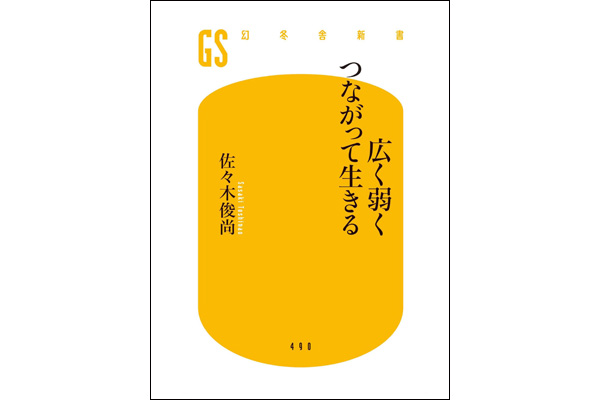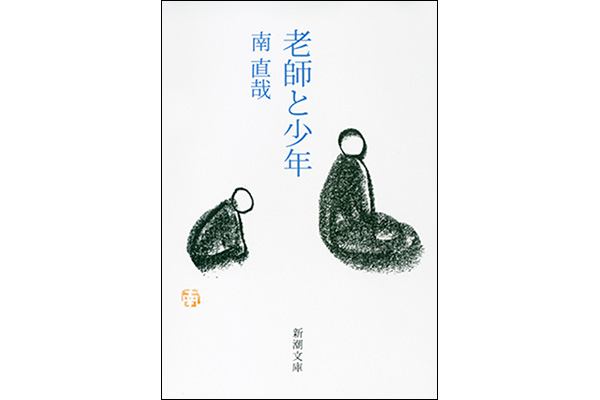
「死を見る」という明確な目的意識のもと、著者は少年期、猫を竹藪で殺している。(『語る禅僧』)
本書では、ネズミを殺す現場を目撃した少年として物語を展開させるが、じつは、そのネズミ殺しこそ著者自身なのである。血なま臭い話、生、自死、生きる意味。そんな話が老師を七夜にわたり少年が訪ねるというダイアローグで語られる。
殺生の場に立ち合うとき、人間は、自身を「裂けたもの」「欠けたもの」として自覚するという。ここで気をつけねばならないことは、何かが裂けたのではない、何かが欠けたのでもない、ただ「欠けた」ということだ。
「欠ける」といえば、「何が」あるいは「何に」欠けているのかという文脈で語られるのが通常だ。しかし著者は言う、「ただ欠けている」のだと。
われわれは常に自分には何が欠けているのか、自分は何に欠けているのか、と問う。この「自分」から始まる問いを著者はまず否定する。さらに進めて、自分が生きているのではない、ただ生きている――自分という形で生きざるを得ない存在を人間と呼ぶに過ぎないのだ、と。
最後に語られる言葉がいい。「生きる意味より死なない工夫」。大切なのは答えを求めることではなく、答えがわからなくても生きてゆく、ということだ。
著者は1958年生まれ。早稲田大学を卒業し、大手百貨店に就職するも、程なくして曹洞宗大本山永平寺にて出家。母は泣き、父は「結局、こうか」とつぶやいた。今は恐山にて死者を弔い、死者と共に暮らす。
本書を、こころ安まり癒されると評する向きもあるが、それ以上に、穏やかではない一書とするべきか。