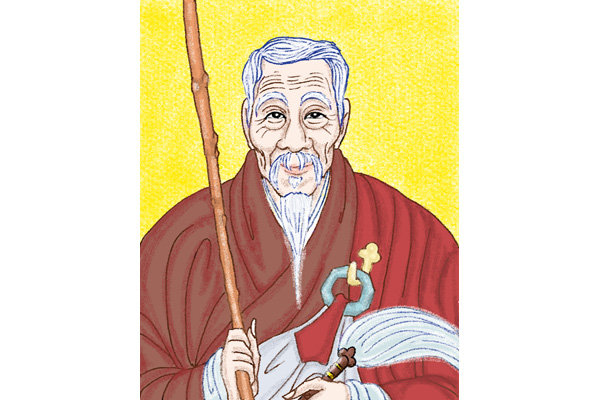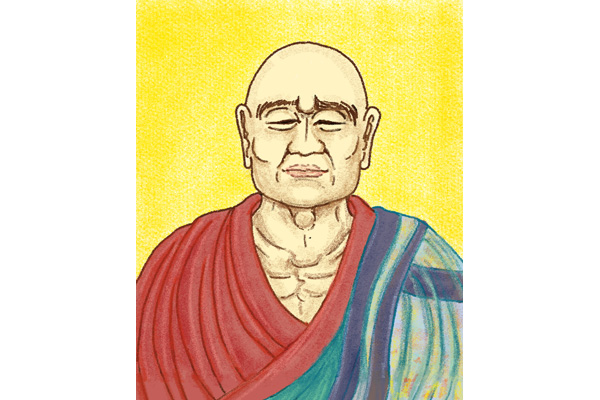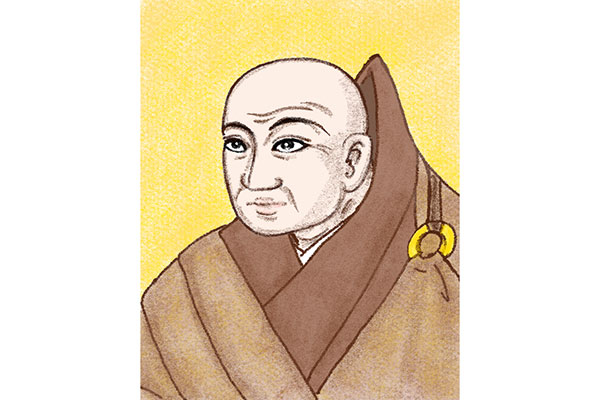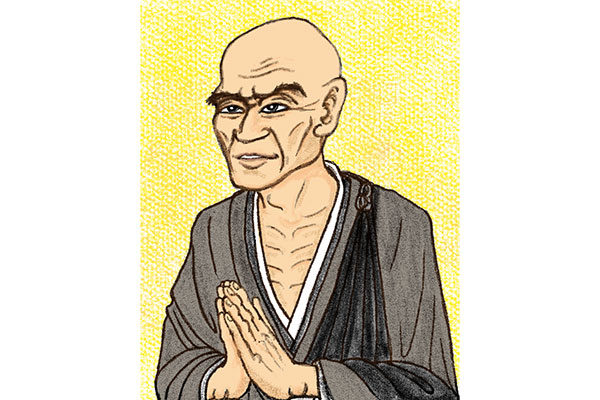大徳寺を死守

臨済宗大徳寺派の大本山大徳寺の塔頭のひとつ。開基は千利休七哲の一人、細川忠興(画像・AdobeStock)
さらに、酷いことに利休の首は、大徳寺の金毛閣から引きおろされた利休の木像の足もとに、これ見よがしに置かれます。そして聚楽第近くの一条戻橋に晒されたのです。
それでも気がすまなかった秀吉は、木像を安置した大徳寺伽藍の破却を命じたのです。
その使者になったのが細川忠興など四人です。彼らは破却命令を伝えたのですが、彼らの前に立ちふさがったのが古渓でした。
古渓は、四人の使者と対面すると、
「大徳寺を壊すなら、死をもって抗議する」
と懐中から短剣を取り出して、決意を示したのです。
使者たちは、一身で大徳寺を守ろうとする古渓の決意に感激しました。そして、秀吉を説得して、大徳寺の破却を思いとどまらせたのです。
使者たちも秀吉も、心の中では古渓のような硬骨漢を尊敬していたようです。
翌年の文禄元年(1592)に秀吉は、秀長の冥福を祈るために郡山に大光院を建てると、古渓を迎えていたのでした。
文禄5年(1596)8月、古渓は急病になったのですが、よほどの重態であったのでしょう。弟子から遺偈を求められると、次のような偈を書き与えています。
「六十余年、胡喝乱喝す。末後の転機、一喝を作さず」
(六十余年も、漫然とした喝を放ってきた。いよいよ命が終わる転機にあたって、今さら一喝でもあるまい)
この偈からすると、古渓は弟子たちに対して、しばしば喝をあびせて厳しく指導していたのでしょう。その自信ぶりを「漫然として喝を放ってきた」と逆の表現でしているのです。
この遺偈を書くと、古渓は亡くなったのです。ところが6時間ほどして蘇生して、集まっていた人を驚かせたといいます。
それどころか息を吹き返すと、何ごともなかったかのように、平常どおりに説法したのでした。
古渓は、それから半年ばかり存命して、慶長2年(1597)、66歳で亡くなります。
その間、後陽成天皇から、「大慈広照」という禅師号を賜っています。
千利休の禅師となって、禅の心をとおして「侘び寂びの茶道」に導いたばかりか、体を張って大徳寺を守ったのが、古渓宗陳という人物だったのです。
バックナンバー「 日本仏教を形づくった僧侶たち」