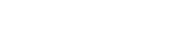日米民間外交の推進
栄一の偉業で特筆すべきは、アメリカとの民間親善外交を推進したことでしょう。
栄一は生涯に4度、渡米しています。最初は明治35年(1902)で、このときはセオドア・ルーズベルト大統領と会談をしました。日本の軍隊と美術を称賛する大統領に対し、栄一は「日本の商工業についても褒めていただけるよう努力します」と応えたといいます。しかし、それから間もなく日米関係は悪化の一途をたどります。
明治37年(1904年)に日露戦争が勃発すると、アメリカは日本を経済的に支援し、ルーズベルト大統領は講和の仲介に立ちます。というのも、戦後、ロシアが満州の利権を日本に譲った場合、日本はアメリカと満州を共同経営すると約束していたからです。ところが日本は約束を破り、単独経営に乗りだします。
またこのころ、カリフォルニア州などに日本人移民が多数流入していました。日本人は生魚を食するなど、白人と生活習慣が大きく異なるうえ、アメリカ社会に積極的には交わろうとしません。しかも安い賃金で長時間勤勉に働くので、白人たちは職を奪われるかもしれないと心配し、排日の機運が高まったのです。明治39年(1906年)にサンフランシスコ大地震が起こると、学校が被災して教室が足りないことを理由に、日本人学童は公立学校から閉め出され、東洋人学校への転校を余儀なくされました。
こうした状況を危惧した外務大臣・小村寿太郎は栄一に対し、民間の力で日米関係を改善してほしいと、ひそかに依頼したのです。そこで栄一は明治41年(1908年)、東京・大阪・京都などの商業会議所の主催というかたちでアメリカの実業家たちを日本に招き、自宅でもてなすなどして親善に努めました。さらに翌年、50余名の渡米実業団の団長として、3カ月にわたってアメリカの約60都市を回り、日本を理解してもらおうと働きかけたのです。

渋沢栄一が賓客をもてなすために使った洋風の茶室「晩香廬」(ばんこうろ)
しかし日本軍は日露戦争後、アメリカを仮想敵国と考えるようになっていました。このまま関係が悪化すれば、日米戦争もあり得ます。けれども栄一は「平和こそが経済を発展させ、人びとを幸せにするのだ」という信念をもっていました。そこで、日米関係委員会や太平洋問題調査会などの結成を呼びかけて、民間の立場からアメリカとの関係改善に尽力し続けます。
それでも関係悪化に歯止めはかからず、大正13年(1924年)、「排日移民法」がアメリカ議会を通過してしまいます。そんななか、昭和2年(1927年)、親日家の宣教師シドニー・ギューリックが「親善は気長にやらなくてはいけない。まずは両国の子どもたちが相知り親しむことが必要だと思う。そこで日本の子どもにアメリカの人形を送りたい」と相談を持ちかけてきました。喜んだ栄一は日本国際児童親善会を創設、日米間で人形の交換による親睦を図ったのです。
それから十数年後、残念ながら日米両国は全面戦争に突入してしまいます。しかし、栄一の進めた日米親善活動は間違いなく尊いものであり、その揺るぎない平和希求の精神は、現代の私たちも学ぶべき点が多いのではないでしょうか。